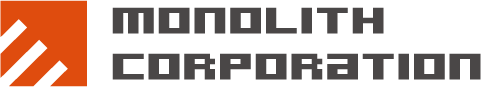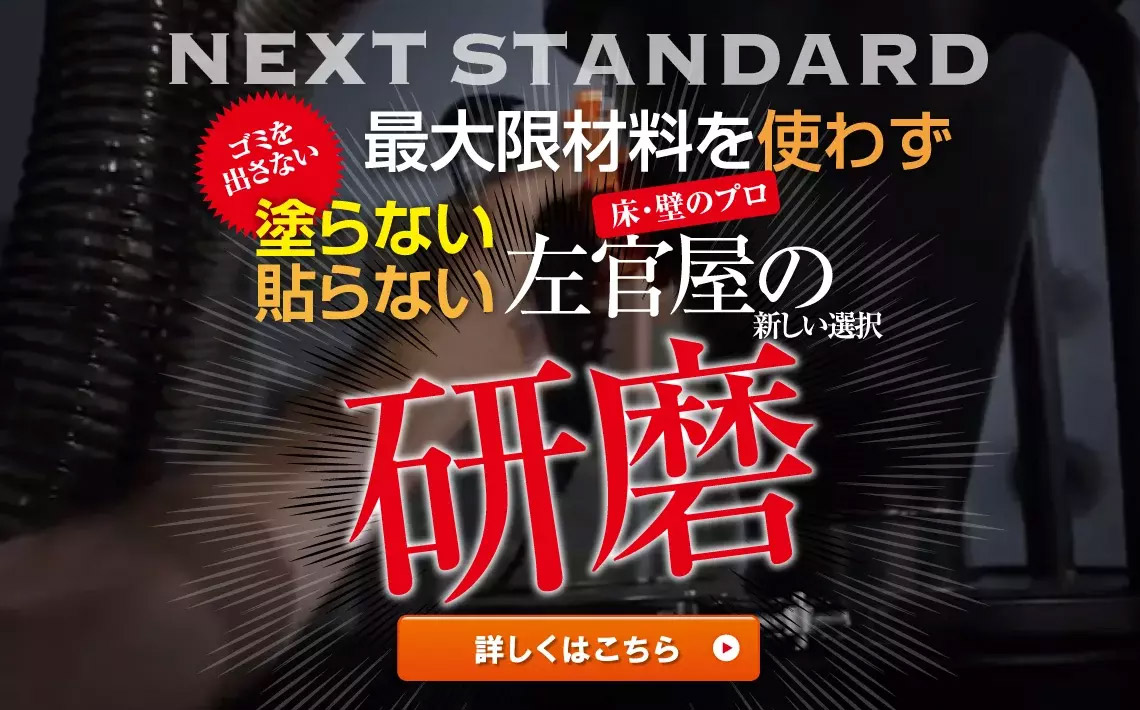NEWS
2022.11.29
コンクリート床仕上げが進むべき道。

モノリスコーポレーションは
「左官・土間工事」において最先端施工を提案する、国内でも唯一のコンクリート床総合ソリューション企業です。
2021年には、
物流床倉庫の直仕上げとして多くの実績を残してきた「KL工法」がNETIS登録。
また、露天下でのコンクリート仕上げの急乾燥を防ぐ、再振動機能付き液体散布機「MecLeen(メクレーン)」を自社開発し、特許を取得しました。
現在我々が力を注ぐのは、「メクレーンポリッシュ工法」。


コンクリート床の表面を全面磨き整えることを前提とした施工プロセスで、非効率極まりない防げるはずの手直しの抑制、余分な労力を徹底的にカットする最も合理的なコンクリート床仕上げの工法です。
この回では、モノリスコーポレーションの代表取締役であり、日本床施工技術研究協議会の理事を務める亀井が、
「なぜこれからの時代にポリッシュ(研磨仕上げ)が適すのか」を本気で解説しました。
この様な方にご覧いただきたい内容です。
✓土間の手直しに頭を悩ませるゼネコン、左官工事会社、土間工事会社
✓単価を上げたい、付加価値を付けたい土間工事会社

新築現場に「研磨・斫り」は必要ないという固定観念


亀井:我々が、コンクリート床の表面を研磨で仕上げる工法を、あえて「ポリッシュ」と呼ぶのには深い理由があります。
もともと研磨というのは業種でいうと斫り工(はつりこう)の仕事で、斫りというのは「新築現場にあってはならないもの」とされています。
斫り業というのは解体の一種ですから、きちんと図面通りにつくっていれば、壊す必要はないだろうということです。
しかし、実際には新築現場でも斫り工は入ります。
それは紛れもなく不具合が多いから。
不具合が多く土間や壁を修正しなければならない状況があるからなんです。これについては後ほど詳しく説明します。
ともあれ、そういう理由で「きちんと工程通りにやっていれば、本来研磨は必要ない」という根深い固定観念があるので、そこでいくら我々が「全面研磨仕上げが合理的」と伝えても、違和感を払拭するまでのハードルは非常に高いのです。
だから研磨とは言わずに、あえて「ポリッシュコンクリート」と呼び、印象を変えているのです。
誰のせいなの?40年続く犯人探し
もっと言えば、「雨打たれなら表面を研磨するのはわかるけど、雨も降っていないのになぜ研磨が必要なのか」というのが、我々が対峙する永遠のテーマなんですよ。
研磨が入る=誰が悪いの?
という話になるので、犯人探しが始まります。
そうすると大概容疑者は土間屋にされる。
なぜなら…一番最後まで手を掛けているのは土間屋だからですよ。
だから斫り屋が入った=土間屋が悪いという図式。
それがこの30~40年、ずっと続いているのです。
本当に土間屋が悪いのか?

しかし大事なのは事実の直視と、真の原因の追求です。
手直しが入るのは本当に土間屋のせいなのか、土間屋だけの責任なのか。
ここを真剣に追求していかない限り、正直に言ってコンクリート床仕上げの不具合は減らないし、土間屋の過重労働も解決しません。
例えばよく不具合の原因として挙げられるのは「レベルが間違っていた」「そもそも基準を間違えていた」など。
その結果打ち直すことになるのですが、実は最も根本的な要素が見過ごされています。
この10年で、生コンの材質が変わってきたということです。そこには誰もメスを入れない。
表現を変えれば、ここに意見しないことこそが土間屋の弱点とも言えるでしょう。
生コンの強度が著しく変化した
では生コンはどう変わったのか。
生コンは地震発生の度に改良され、もっと強いもの・もっと硬いものへと移行してきたことで、強度が極端に上がっています。
「硬ければ折れない・割れない・壊れない」という考え方が、ストレートに材料に反映されました。
コンクリートの強度はN(ニュートン)で表されますが、今の建築で一般的に使われているのは大体18~45N位。
しかし、現場で何が起こっているかというと、
金鏝(ゴテ)仕上げという工法だけが決まっていて、生コンの硬さは施工当日まで殆ど知らされていない。
確かに見積り時に知らされている場合はあるけれども、それはゼネコンにしか知らされていない。
見積り時に「生コンの強度は45Nで見積ってください」と伝えてくださるゼネコンは極僅かです。
「とりあえず金鏝仕上げの数字で入れておいて」というと、我々も一般的に18Nとか21Nの比較的扱いやすいコンクリートをイメージして単価を入れます。
ところが、当日届くコンクリートは想定外の強度。
ちなみに45Nのコンクリートで打設した時と、18Nで打設した時とでは労働力は10倍近く異なります。
それにも関わらず金鏝仕上げというカテゴリーで同じ括りにされてしまう。
これが大きな問題なのです。
硬いコンクリートはなぜ労力がかかるのか

強度が高いコンクリートというのは、異常に粘性がありネバネバしています。
我々は重い、硬いと表現しますが、コンクリートの中に埋まった長靴が抜けなくなる程の粘性がある。
それにより、作業者の足腰にかかる労力、作業時間は何倍にもなるのです。
18Nでは長靴がスポっと抜けても、45N以上は田んぼの中で農作業しているのと同じ状況。足は上がりません。
面積が1,000㎡もあれば、作業中に何回足を抜くでしょうか。
工期内にその労力をカバーするためには人数を増やすしかない。
5人で賄えるはずだったところを、10人でやる。
そうしていかなければ品質が担保できない。
コンクリートの強度は変わっても、金鏝仕上げという工法が同じであれば見積りには平均的な人数が記載され、当然左官屋、一次請け会社の感覚で決められてしまう。
では3人だったところに、倍の人数、6人入れればいいのかというと、実はそれも予算的に叶わない。「分かった、1人増やして4人だったらなんとかするから」と言われても、4人でも無理なんです。
ヘタをすれば7~8人いないと終わらない仕事を、人数的な不利でやらせてしまうわけです。
そうすると何が起こるかというと、不具合が出る。
これが、コンクリート床仕上げの不具合が無くならない真の原因です。
コンクリートというのは、固まる前の作業中は不具合に気付きにくく、硬化してから不具合が顕著に現われる非常に繊細な材料。
作業中は、コンクリート表面に不陸が出ないよう最大限の配慮をしていても、コンクリートが硬化する過程で沈降などが起こり、表面に凸凹が発生します。そのままの状態で仕上げ材を貼っていくと、当然下地に凹凸があるので仕上げ材が波を打って、じゃあ「これは誰の責任」=土間屋でしょ、となるわけです。
これが今のこの業界の現状です。
土間工事は誰が見積もるのか問題

土間の不具合、手直しについては責任転嫁が横行してるんですよ。
単価を承諾したのは下請けですから、一次会社からは「やれるって言ったよね?」と追求される。そしてまたここにも歪みがある。
土間屋が仕事を取ってくるのではなく、
左官屋がゼネコンから仕事を取って→左官屋が土間屋に発注している
だからおかしなことになる。
左官屋が仕事を取れるかどうかが最も重要で、土間屋の気持ち(単価)はどうでもいいんです。
考えてみてください。例えば10万㎡の建物だったら、単価50円上げるだけで500万円違う。しかしその50円を乗せると他社に仕事を奪われてしまう。
本来人員を増やすために必要なお金が、仕事を取るために削られていく。
何十年もこの繰り返しなんです、左官屋と土間屋の歴史は。
一発直仕上げはもはや「幻想」

これらを変えていかなければ、一発でその日のうちにキレイに仕上げるなんて無理。
メクレーンポリッシュ工法の発想が生まれた原点です。
固まってからキレイに整備した方が合理的でしょうと。
そもそも金鏝仕上げは真冬の0℃でも、真夏の40℃でも、仕上げ方は同じ。
…ってそんなワケないでしょう!(笑)
気温が40℃も違うのに、なぜ仕上げ方が変わらない?
変わらないハズがない。
暑ければ暑いなりに人員が必要、寒ければ寒いなりに固まるまでに時間がかかる。そこに誰もフォーカスしないんですよ。
それだけではありません。
生コンプラントを一社で統一してくれるならまだ「傾向と対策」が取れますが、現実は「明日はカメイ産業、明後日はカワムラ産業、その次は…」と、毎日違うプラントの性質の違う生コンが届くんですよ?
水も出方も固まり方も何もかもが全て違う。そりゃあ均一にはならないですよ。
土間屋は試合開始前から負けている
土間屋は毎日が出たとこ勝負で、非常にリスクが高いことをやっていますよ。
でもそれも、
・コンクリートの性質が変わった
・気候変動で気温が変わった
もうこれまで通りでは通用しない、時代が変わったんです。
蕎麦打ち職人もそうでしょう。夏と冬で水の量は違う。
職人が自分で調節しますよね。
左官屋にはそれが出来るんですよ!
自分たちがやりやすいように、気温に合わせて自分たちで材料を練るから。
でも土間屋は当日届いた、それも勝手に指定された生コンでやれという仕事だから、始める前から負けてるんです。
自分で自分の首を絞めた
これは、一発直仕上げという工法を流行らせてしまった不運な結果でもあります。
その日のうちに仕上げられる、出来ると言い過ぎてしまったがために、土間屋が自分で自分の首を絞めこうなってしまった。
しかし今の施工環境のあらゆる条件を考慮すれば、夜遅くまで残ってコンクリートが固まるまで待って仕上げるのではなく、
騎乗式の円盤掛け程度まで終われば、それ以降は磨いて最終仕上げをする方が時間のロスもないし、働き方改革にも近づけるでしょう。
その方が、品質も担保できる。
毎日硬さ、温度が違う「生コン」を扱う難しさが、もう限界に来ているというのが、このメクレーンポリッシュ工法のテーマです。
これからの時代は研磨が最適だというのは、ある意味でそうせざるを得ない物理的環境の変化があるからなんですよ。
責任を擦り付け合い、歩み寄らない左官屋と土間屋

私は、この話を今までずっと伝え続けています。
今年の初めには日本床施工技術研究協議会でも提案しました。
業界全体で足並みを揃えて取り組まなければ変えられないほど深い問題だから。
そしてそれはなぜか。
土間屋は一次会社ではないからです。
左官屋と土間屋は、歩み寄れないんですよ。
土間屋は責任を全部左官屋に押し付ける。施工して不具合が出たら「知らないよ、左官屋が直せ」と。左官屋は「出来るって言ったのはそっちだろう」と。
永遠と責任転嫁の繰り返し。
そして、この状況を打破したのが川村工業です。
「それなら左官も土間も、自社でやってしまった方が良い物ができるのでは?」と。
さらには「手直し」まで含めて全て自社一括でやる、という方法を実現したんですね。
状況が変わらないなら、自分たちでやってしまったほうが
良い物ができてそれでいて早い、トータルでかかる費用も変わらない、責任の所在も明確、加えてゼネコンはラクできる。我々も管理しやすい。
必然的な流れでそこに辿り着きました。
今までのやり方を続けても、土間屋の人材は育たない
労働問題に切り込んでいきましょうか。
土間屋には意外と若い人っているんですよ。だた、継続しない、できないんです。
土間屋の初任給は他職種と比べて高いんですね。
仕事さえ覚えれば、中学卒業してすぐ例えば16歳などでも50万円位は稼げてしまうんです。その代わり朝から晩までずっと現場にいますから、一生勤めようとは思わない。
最近ですよ、22時以降は帰ってくれとゼネコンから言われるようになったのは。
なので、建設業の中でも若い子は土間屋に来る。
また昔からやっているベテラン層、もうシニア層ですがその年齢の人たちもいる。
いないのは中間層です。ここが問題。
結局2番手3番手がどんどん独立していって、そのサイクルも早い。

仕事ができるようになるまでが早いんですよね、単純作業が多いので。そこから先は、これまでお話した通り非常に深いのですが。
なので手っ取り早く稼げてしまって、個人事業主ならそこから税金を払わなかったり…、そういう社会の仕組みがよくわからないという人が沢山います。
「1週間は無理だけど2〜3日なら動けるよ」という、気分で働く人が多いんです。
でもそれでは社会保険への加入やキャリアアップシステムの登録とか、国が言っているようなシステムの導入は無理なんですよ。
ですから8時に来て17時には終わりにする、それ以降は研磨で整えるというプロセスが理に適っているのです。
土間屋になぜ付加価値が必要なのか

ちょっと違う観点から見ると、土間屋は1ヶ月のうち働く日数が20日くらいしかありません。土日、祝祭日は生コンプラントが休みなので。
梅雨の時期だと雨が降って実質15日程度。
ということは、1ヵ月の給料を15日で稼げるだけの単価、そういう保証をしていかなかったらこの業界に未来は無いですよ。
そのためには我々が提唱するKL工法のように、施工を一つ一つ数値化して、再現性の高い作業に変えていき、生産性を高める新しい技術も取り入れて付加価値を付けて単価を上げていくことが必須なのです。
そこに業界全体が賛同していく流れを生むために、私はいまこうして会合などに出席しているのです。

いくらこのような話をしても、「いや、うちならその単価でできるから」「頑張れるよ」という業者が出てくるので、いつになってもまとまらないんですね。
やる気云々じゃなしに、愚痴とか責任の擦り付け合いでもなく、仕組みを持ってゼネコンにも一次会社にも提案しなければ、話を聞いてもらえるわけがない。
現実を動かしていくには「根拠」がないと。
これは昨今騒がれている建設業の週休二日制にも直結する問題ですよ。
足元を固めない限りそこには到達できないんです。
エンドユーザーが欲しくなるものを創り出す
我々は、メクレーンポリッシュ工法は、業界が賛同しなくても、エンドユーザー、世の中が賛同すると確信しています。
社会的背景を考えた時の様々なメリット、そして断然高まる品質。
お金を払うお客さま(施主)にとっても、メンテナンスをほとんど必要とせず面倒なことがない。
試行錯誤の末、現状ではこれが最もスピーディーにあらゆる問題を解決していく手段であると、考えています。
メクレーンポリッシュ工法の詳細
積層構造の手直しを無くす!工程の大幅な短縮、過重労働を劇的に改善